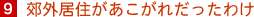
 |  |
 |
| 松村: |
話が飛びますが、北京で起きていることを紹介します。あちらでは政府が土地所有者で、都心部の高く貸せるエリアには、旧来の密度で低所得者層にはあまり住んでいて欲しくないのでしょう。例えば、胡同(フートン)と呼ばれる伝統的な低層都市住宅地域には、昔からの住民が低密度で暮らしてきた。でも、現在は都心の一等地になったので、行政としては、そこに超高層ビルを建てたいと考えるわけです。
 |
再開発で1000世帯以上が住んでいた住宅地があっという間になくなる。そこに住んでいた人々には、すごく遠い郊外団地へ移ってもらう。そうした郊外住宅地に行ってみると、100棟くらい同じタイプの集合住宅が延々と建っているだけです。そうした郊外住宅地を見ていると、それは居住の問題を解決するためではなくて、不動産経営のために建てられているとしか思えない。
|
同じような状況は戦後の日本にもあったのだと思います。つまり、本当は別の優先課題があって、住宅問題の解決を装いながら郊外居住を進めていったんじゃないか。駅前団地に住むということには、新しい生活が始まるという期待があった、と記述されていますよね。でも、それはひょっとすると、親から離れて生活ができる、核家族化した生活ができる、という開放感だったのではないか。戦後、郊外住宅が広まっていったのは、そういうことに目をくらまされていたとも言えるんじゃないかと思うのです。
|
 |
| 角野: |
もう一つ思い当たるのが、郊外ニュータウンへ出て行った人は、町なんかどうでもよくて、むしろ、そこでの生活と、設備にあこがれて出て行ったのではないか。ステンレスキッチンがあるらしいとか、水洗便所があるらしいとか。いずれにせよ町のことは考えていなかった。
そうした成り立ちが今日の郊外の状況に直結しているのだと思います。でも、戦後の郊外住宅地ができはじめて40年も年月を重ねてきたわけですし、何よりたくさんの人々が暮らしているのですから、放っておくわけにはいかない。
郊外を維持するためには、ブランド作りが欠かせないと思うのですが、じゃあブランドをどうやってつくるかという時に、先ほど申し上げたように、通りでブランドを作っていくとしましょう。例えば、代官山のブランドが生まれているのは、ヒルサイドテラスがあるからですよね。あそこはかなり低容積です。そこで、通りに面する建物の容積率を低く抑える規制をかけたとしますよね。すると、低容積にすることによって失われていることを街全体が負担しなければならない。ほかの制限をかけるときにも同じことで、そうして発生するマイナスを町としてどうやって負担していくのか、といった仕組みづくりも必要になっていくと思います。
|
|