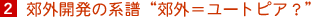
 |  |
 |
| 角野: |
近代における郊外開発というのは、当初はユートピアづくりでした。ハワードであれ、日本の明治中後期からの郊外開発であれ、全てそうです。それも中産階級向けということが大前提になっていて、例えば、国内では阪神間にユートピアが生まれました。そこでは、超お金持ちの郊外居住が理想像としてイメージされています。「あなたたちもがんばったらそんな暮らしできるんじゃない?」ということで、小林一三が率いる阪急をはじめとして、電鉄会社が郊外開発の大衆化路線を引っ張っていきました。また、ある時期には、単に住むだけではない固有のテーマを持った住宅地、一種の商品的住宅地も開発されます。例えば、伊丹養鶏村、石橋温室村などです。おそらく、昭和10年頃がユートピア型郊外開発のピークでしょう。
しかし、第二次世界大戦が勃発して、戦後は深刻な住宅不足に陥ります。とにかく住宅を数多く供給しなければいけない状態になって、都心であれ郊外であれ、とりあえず世帯数と同じ数だけ住宅が必要なんだという風潮の中で、郊外開発が進められます。結局、戦後のニュータウン開発は、この出発点から一歩も踏み出すことができなかったと思うのです。千里ニュータウンの場合ですと、その目標は、大阪へ通勤する人々の住宅をいかに大量に短期間に供給できるか、ということに尽きるわけです。
そうした巨大な郊外開発に、「ユートピアづくり」という考え方が受け継がれてきたかというと、はなはだ疑問です。確かに、千里ニュータウンに関わった技術者は、集合住宅の配置や戸建住宅地のクルドサックの配置など、様々な意欲的試みをしている。彼らは、まさに理想の住宅地を作ったという自負もあったでしょう。ですが、そこに住んだ人にとって重要なことは、そうした計画上の試みではなくて、そこそこ便利なところに家が欲しいという願いをかなえることでした。言い換えれば、千里ニュータウンの緑や自然、あるいは歴史的文脈には関心がなかったと思うのです。
千里ニュータウンは、公的開発ですからインフラはよく整備されていて、50年、100年と永らえるだけの基盤を持ち合わせています。そのため、千里ニュータウンまわりでは、コバンザメ的郊外開発が民間によって進められてきました。田園の中の住宅地が郊外であるとすれば、もはや千里ニュータウンは郊外ではなくなってしまったのかもしれないですね。当初はユートピア的な住環境の計画であったかもしれないけれど、結局は都心に出撃するためのベッドタウンになっちゃったわけです。
こうして、郊外開発の最先端は常に市街地の縁辺部に発生していくわけですが、そこにはよい住宅ができない。住み手が、都心との距離だけで住宅の価値を測っているからです。本当はもう少し都心近くで生活したいけれど、ここならなんとか一戸建てが買えるから、という理由で住宅を購入している。その結果、戦前の郊外なら100坪くらいはあった郊外住宅は、どんどん規模が小さくなっていって、結局、郊外住宅自体がユートピアなんてものではなくなってしまったわけです。
一方、ディベロッパー側は、供給戸数が増えていく住宅市場の中で、開発した住宅地を商品として差別化をしていく必要がある。商品としての魅力とは何か、ということを考え始めるわけです。まずは、便利です、自然が豊富にあります、ということをアピールする。でも、売っている本人が不便であることを一番知っている。ですから、不便に見えるかもしれないけれど結構便利よ、とアピールすることになる(笑い)。
次に、そうした当たり前のこととは違う魅力や個性をどう作っていくかが問題となって、テーマタウン的開発が進みます。そうしたテーマ探しを行ってきたのが昭和50年以降と思います。それらのテーマの中には、住宅地ではなく、商業施設や文化機能をミックスして本気で町を作ろうというものもありました。これは主に公的開発に見られます。ところが、民間開発の場合は、本当はそうしたいけれども、そうもいかない。公的開発でできるものが、民間開発ではできないわけです。それじゃあ、ハードではなくて、ソフトで競争しようとなってくる。でも、そこには、かつてユートピアを求めたような理想があるかというと、疑問を感じざるを得ません。
|
|