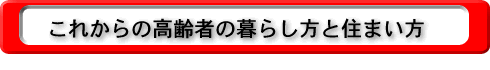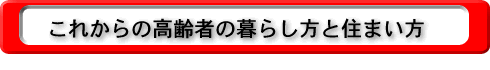|
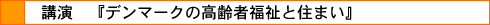 |
 |
 |
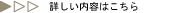 |
|
|
| |
|
 |
| ◆ デンマークの高齢者福祉の現状 |
| |
1.二世帯住宅を提案した時代
デンマークでは高齢者を「介護の対象」としてではなく「生きる主体」としてとらえており、高齢者福祉の基本理念は「自立支援」である。それを制度として支えているのは高福祉高負担、地方自治、公的セクターを中心とした「大きな政府」による普遍的な社会保障のありようである。小規模を目安とした福祉地区で、民間セクターやボランティア活動などによって介護が行き届いている。
高齢者福祉の基盤 自立:基本理念は「自立支援」と「自己決定」
⇒高齢者は「生きる主体」であり、「介護の対象」ではない。
政策:高福祉高負担
⇒GDPの52%が税金、そのうち43%が社会保障へ
(日本はGDPの28%が税金で、18%が社保へ)
地方分権
⇒人口1〜2万人を目安とした福祉地区
公的セクター中心
⇒公的セクター(コムーネ=市)がサービスを提供
⇒自由選択Frit valg の開始によって、民間企業も参入
⇒上記フォーマルケアのスキマを埋めるものとして
インフォーマルケア(ボランティア活動)もさかん
⇒労働市場への参画は男女ともに80%前後。
配偶者間には扶養義務があるが子供には親の
扶養義務はなく、同居率は4%足らず。
世代間の介護はないが精神的には支えとなっている。
|
|
◆プライエム増設の時代から、腐敗へ |
| |
1925年に高齢化社会(65歳以上の高齢者が全人口の7%を占める)を迎えたデンマーク。戦後の経済成長を背景に、1960年代にはプライエム(日本の特別養護老人ホームに相当)が増設されたが、その大規模化と集団処遇、与えるだけの過剰ケアのなかで高齢者は命の輝きをなくし、いつしかプライエムは「死への待合室」のようになってしまった。 |
| |
|
| ◆ 1988年、プライエム(特養)の建設を凍結 |
| |
その頃の社会・経済状況は、高齢者増加、財政逼迫、施設ケアは高くつく、という三方ふさがりであった。世にいう「福祉国家の危機」を乗り越えるべく、デンマークでは1979年「高齢者政策委員会」が結成された。1980年代初頭に報告書が出され(有名な高齢者三原則もその中に含まれていた)、この報告書を基盤に、1988年以降プライエムの新規建設は禁止された。
|
|
| ◆ 施設「プライエム」から、高齢者住宅へ |
| |
プライエムの建設凍結後、その代替として建設されたのは「高齢者および障害者住宅法」に基づく高齢者住宅である。よい住宅を供給して、住む人のニーズに合わせて「在宅ケア」としてサービスを届けて、最期まで地域で住み続けることを目指す政策が実践に移されたわけである。1987年より近年にいたるまでの高齢者居住の変化を見ると、旧型のプライエムは減り高齢者住宅が増加して、この15年間でその数が逆転している。
|
|
| ◆ 住宅のみで、はたして地域居住継続は可能か?! |
| |
しかし、本当に高齢者住宅のみで「住み慣れた地域で最期まで住み続ける」という地域居住継続が可能なのだろうか?
松岡はデンマークの知見より、「『在宅で最期まで』の七つ道具」を取り上げる。なかでも、高齢者住宅の近くには「交流と役割づくり」の場であるアクティビティハウスの存在が重要であり、24時間ケアの整備や地域リハビリは必須であり、これによって初めて、『在宅で最期まで』戦略が可能となるのである。
|
|
| ◆ プライエボーリ(介護型住宅)の登場 |
| |
一方、どうしても自宅での生活が困難な人のために、より自宅に近い環境でしかも介護が受けやすい環境にある住まいとして「プライエボーリ(介護型住宅)」が登場した。これは、高齢者住宅という制度の枠組みのなかで「より安心な住い」をつくろうとしたものであって、決して「施設」ではない。住人は高齢者住宅に家賃を払って住むテナントであり、個別のアセスメントを受けて個別ケアを受けることとなる。これは、在宅での暮らしとなんら変わりがない。
|
|
| ◆日本とデンマークにおける高齢者施設と、高齢者住宅の供給量比較 |
| |
イギリスをはじめとする高福祉国家においては、高齢者居住整備(施設も住宅も含めて)の目安として、10%以上(65歳以上高齢者人口に対する割合)を目標においている。例えば、イギリスの保護住宅sheltered
housing の整備率は10-15%が目安とされた。
こうした世界標準を念頭においてデンマークと日本を比較すると、デンマークでは住宅整備率は6.1%であり、施設にいたってはそれよりも低い5.2%となっている。
一方日本においては、施設3.8%、住宅0.5%という淋しい状況であり、高齢者居住全体としての整備の遅れとともに、とくに住宅についてのあまりにも貧弱な状況を重要な問題点として指摘することができる。
そもそも「介護保険」が目指すのは、高齢者の自立支援と在宅生活継続である。2001年6月『2015年の高齢者介護』(高齢者介護研究会報告書)が発表され、現在介護保険5年目の見直しのなかで、地域包括支援センターや地域密着型サービスの構想が打ち出されている。これらは主にケアよりの話しである。しかしながら、高齢者居住と在宅ケアは地域での普通の生活を継続していくための重要な構成要素である。タテワリ行政の名のもとに分断されるのではなく、高齢者自身の生活の目線に立ったダイナミックな政策立案と制度設計が求められるのではないだろうか。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|