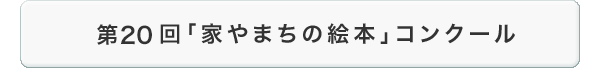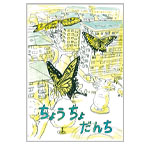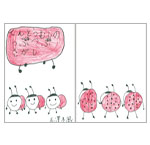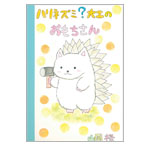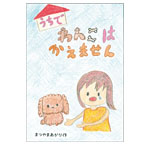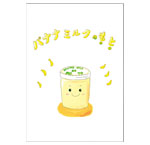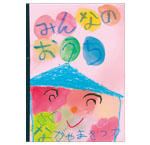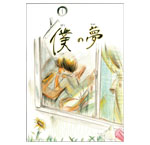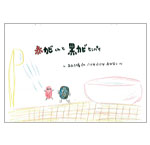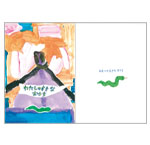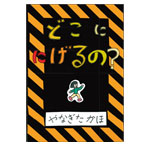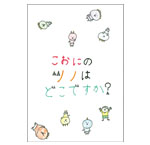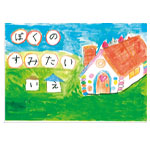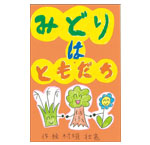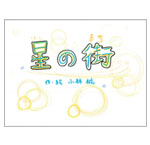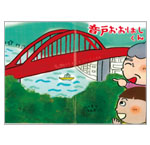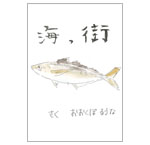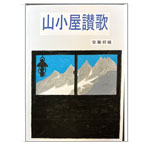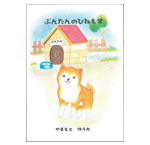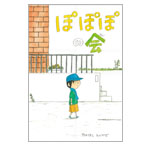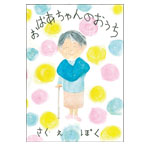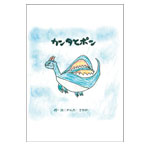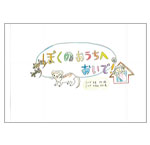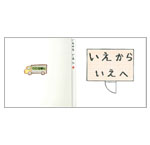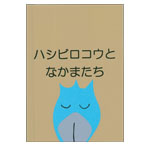���@�]
�@�u�Ƃ�܂��̊G�{�v�R���N�[���́A2005 �N�ɑ�1 �J�Â���A�R���i�Ђł����f���邱�ƂȂ����N���{���ꑱ���A�����20 ��ڂƂȂ�܂��B�R���ψ����́A����܂Œ��N�ɓn��s�͂��ꂽ���V�I���q�搶���璇���q�Ɉ����p���܂������A�R���̕��j�͈�т��Ă��܂��B�܂�A�Ƃ�܂��ɑ����҂̑z���∤�����`����Ă����i�ł��邱�ƁA���̑z�����F�ŋ��L�������Ȃ�悤�ȓW�J�ł��邱�ƂȂǂ��܂��Ȋ�Ƃ��Ȃ���A��{�I�ɂ͉����i����ЂƂ�������Ɠǂ܂��Ă��������A�R���ψ��S���łĂ��˂��Ɉӌ������킵�đI�т܂����B
4�̕���i�q�ǂ��̕��A���w���E���Z���̕��A��l�̕��A�q�ǂ��Ƒ�l�̍���̕��j�ł̎�܍�i��ʂ��đ�Ȃ��Ƃ������������܂��ƁA�ȉ��̒ʂ�ł��B
1�߂́A���܂��܂Ȏ��_�ɗ������݂��݂��������z�̊G�{�́A���̐��E�̑��l����L���������߂ċ����Ă����Ƃ������Ƃł��B���⓮���͒�Ԃł����A�d����S��J�r�܂œo�ꂵ�܂����B�l�Ԓ��S��`�Ƃ������_�ł͑������Ȃ����E�������ɕ\������Ă��܂��B���y��ʑ�b�܂̍�i�́A���傤����ɒ��ڂ��邱�ƂŁA�ꌩ����ӂ�Ă���悤�Ɍ�����c�n���A�݂ǂ�L���Ől�X�̎v�����ɖ��������ł��邱�ƂɋC�Â����Ă���܂����B
2�߂́A�G�̗͂ł��B������܂��̂悤�ł����A���͓I�ȊG�̓V���v���ɐl���䂫���܂��B����A����AI �𗘗p�����Ǝv�����i�������܂������A���i�K�ł́A��`���̍�i�Ɉ��|�I�Ȗ��͂�����܂����B�܂��A�H�v���Â炵�����k�ȉ��H�̔�яo���G�{�́A�����̎��ԂƘJ�͂�������ꂽ���Ƃ����������A���̎p���ɓ������������ł��B�R���ψ��ꓯ�A�y�[�W���߂���A�������������тɋ����̐����グ�Ă��܂����B
3�߂́A���̏𑨂�����i�ɂ͋������b�Z�[�W������܂��B�\�o�����n�k���e�[�}�Ƃ�����i�͂��̓T�^�Ƃ����܂��B�n�������Ɋւ����i�����̈�[�𑨂��Ă���Ƃ�����ł��傤�B�U��Ԃ�ƁA�����{��k�Ђ�R���i�Q�ł́A���̂Ƃ��ǂ��̏𑨂�����i������܂����B�u�Ƃ�܂��̊G�{�v�R���N�[�����Љ�f������̂ƂȂ��Ă���A�������͊G�{��ʂ��Ă��̌o���������ƖY�ꂸ�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�Ō�ɁA�{�R���N�[���ɂ͕������܂��Ă����A��҂����܂��B��l�̕��ɑ����ł����A����A���w���E���Z���̕��̎�҂�4�N�O�Ɏq�ǂ��̕��Ŏ�܂���܂����B��i����ׂĔq������ƁA�����ɐ������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���̂悤�ȏ�ʂɗ������̂��A�{�R���N�[�����p�����ĊJ�Â���Ă��邨�����ł��B���N���f���炵����i�ɏo��邱�Ƃ��A�R���ψ��ꓯ�A�S��肨�҂����Ă��܂��B
2024�N10��
��20��u�Ƃ�܂��̊G�{�v�R���N�[���R���ψ���
���m��w�@�����@�� ���q
| �R���ψ� | ���呍�� �F 743��i | ||
|---|---|---|---|
| ���@ ���q | �i���m��w �����Љ�f�U�C���w�� �@�l�Ԋ��f�U�C���w�� �����j |
�q�ǂ��̕� | 237 ��i |
| �u�� �D�q | �i�܂��Â���v�����i�[�j | ���w���E���Z���̕� | 851 ��i |
| �k�� ���� | �i�o�Ŏ� �ҏW�j | ��l�̕� | 23 ��i |
| �L�� �Lj� | �i�ߌ���w�Z����w�� �ۈ�� �y�����j | ����̕� | 36 ��i |
| �u�� ���� | �i���k�|�p�H�ȑ�w �|�p�w�� �@���j��Y�w�� �����j |
||
| ���V �I���q | �i�����w�|��w ���_�����j | ||
| ���V �Ďu | �i���y��ʏ� �Z��� �@�Z��Y�� �ؑ��Z��U�������j |
||
| ���� �N�� | �i�Z����Z�x���@�\ �}���V���� �@�E�܂��Â���x���� �Z�p���������j |
||
| ���� �m�� | �i�s�s���@�\ ������ �L���j | ||
| ���� ���N | �i�Z��Y�c�̘A���� �ꖱ�����j | ||
| �R������ | |||
| ꠁ@ �p�q | �i�i����w ���������w�� �����j | ||