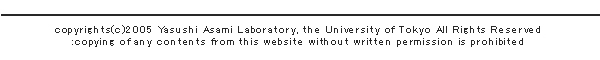斜面都市長崎のまちなみ ―3項道路規定が適用されたまちなみ―
◆都市計画的な視点で長崎市をみる
坂のまちとして有名な長崎.市街地の西側に長崎港を臨み,平地は浦上川と中島川に沿って僅かに存在するのみである.長崎出身の友人が指摘するように,坂が多いゆえにまちを歩いていて自転車を見る機会は驚くほど少ない.市街地の公共交通機関は充実している.市内の路面軌道である長崎電気軌道は市街地の幹線道路上に面的に展開している.運賃は一律100円であり,乗車率は高い.
平地が限られているため,宅地化は斜面に沿って進行した.斜面にへばりつくように家々が建ち並ぶ風景は,長崎特有のものである.街路は整備されておらず,自動車が進入不可能な道は多く存在し,人がすれ違うことが可能な程度の幅員しかない.ところが,かえって幅員の狭さが坂のまち長崎の魅力を高めているように感じられる.
建築基準法によると,敷地は原則的に幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない.斜面に沿って宅地化が進行した長崎において,この原則を当てはめることは困難である.実際に斜面上に存在する道の幅員は4mに満たない場合がほとんどである.このような現状を可能にしているのが建築基準法第42条第3項であり,「3項道路」と呼ばれている.3項道路は,斜面のように物理的に拡幅が困難な幅員4m未満の道路において,幅員4m未満の道路の存在を認める規定である.
本稿では,「3項道路」が適用された斜面都市長崎のまちなみを考察する.なお,長崎県において「3項道路」が適用されている道路に関する図書を入手することは不可能であった.このため,目視により明らかに「3項道路」と思われるものを対象に考察することをお許し頂きたい.
◆斜面に宅地化が進んだ地区
取り上げる地区は以下の通りである.
1.長崎中華街裏からオランダ坂界隈
2.地獄坂界隈
3.風頭公園界隈
4.竜馬通り界隈
5.寺町界隈
6.中の茶屋界隈
これらの地区は,長崎市中心市街地の東側の傾斜地に位置する.今回は,「1.長崎中華街裏からオランダ坂界隈」を取り上げることにする.
◆長崎中華街裏からオランダ坂界隈
長崎新地中華街の南西,湊公園の南側一帯には,「十人町」と呼ばれる住宅地が存在する.湊公園の横を歩いていると,南側に写真1のような階段が見えてくる.写真を見る限り,階段の向こう側に住宅地が存在するとは思えない階段である.坂のまち長崎を楽しむためには,こうした何の変哲もない階段に注意することが第一の要件だ.
階段の先に進むと,写真2のように斜面に沿って階段が続く.階段沿いには,住宅が建ち並ぶ.階段の上り下りの大変さを物語るように,階段の下にはベンチが存在する.さらに階段を上ると,写真3のように長崎市街地を見下ろすことができる.
 写真1
写真1
 写真2
写真2
写真4をご覧いただきたい.十人町の案内図である.案内図には,道路網に大まかな敷地割り,そして火災時に使用するホース格納庫の位置と災害時避難場所が載っている.案内図の道路の部分を良く見てみると,街区を囲む道路に階段が多数存在することがわかる.このため,十人町一帯の敷地は,階段を上り下りしなければたどり着くことができない.街区を囲む道路からは,写真5のように路地が伸びている.路地は斜面に垂直に伸び,路地沿いには住宅が建ち並ぶ.こうした路地を横に見ながら階段を上り終え,後ろを振り向くと写真6のような風景が目の前に広がる.写真6の風景は写真3の風景と異なる.階段を上るにつれて,眼下に広がる街並みも変化して見える.こうした坂道の風景の変化を楽しむことが,坂のまち長崎の醍醐味ではないだろうか.
既述したように,敷地は原則的に幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない.ところが,十人町の多くの敷地はこの要件を満たしていない.幅員4m以上という要件は,防災上と衛生上の観点から課されているものである.特に,幅員4m以上を確保する防災上の理由として,消防車の通行と延焼防止がある.では,十人町において,幅員4m以上という要件は現実的な要件なのだろうか.平地が限られた長崎市内において,住宅地は斜面に広がった.急勾配の道ゆえ,階段の設置を回避することは困難であったと推察できる.階段の存在は消防車の通行を困難にする.ゆえに,仮に幅員4m以上に拡幅する理由として消防車の通行を挙げることは,階段をなくさない限り現実的ではない.また,幅員4m以上に拡幅するもう一つの理由として延焼防止が挙げられるものの,物理的に延焼を防止する手段は幅員4m以上に拡幅することだけでない.沿道の建物を耐火造にすれば,延焼を防ぐことは可能である.問題は,耐火造化することが幅員4m以上に拡幅することの代替手段になりうるかどうかであろう.
十人町のように,物理的に幅員4m以上に拡幅することが困難であれば,既述した「3項道路」に指定することが可能である.さらに,2004年以降「3項道路」の適用範囲は広がった.趣きのある佇まいや歴史を有する幅員4m未満の2項道路においても「3項道路」に指定することが可能である.十人町をはじめとする坂のまち長崎の魅力を高めている要因の一部には,幅員の狭さや沿道の景観が含まれると考えられる.沿道の景観は,長い年月をかけて形成されたものであり,長い年月が景観に歴史と趣きを与えてきた.問題は,こうした要因を定性的に議論するだけでなく,客観的に評価しその真偽を明確にすることである.残念ながら,客観的に評価する方法は確立されていない.そんな中,「3項道路」の適用実績が多い斜面都市長崎は,趣きのある佇まいや歴史の保全と防災対策の両立を如何に図るか,そして両者の関係を定量的に評価するための手がかりを与えてくれるだろう.
 写真3
写真3
 写真2
写真2
写真4をご覧いただきたい.十人町の案内図である.案内図には,道路網に大まかな敷地割り,そして火災時に使用するホース格納庫の位置と災害時避難場所が載っている.案内図の道路の部分を良く見てみると,街区を囲む道路に階段が多数存在することがわかる.このため,十人町一帯の敷地は,階段を上り下りしなければたどり着くことができない.街区を囲む道路からは,写真5のように路地が伸びている.路地は斜面に垂直に伸び,路地沿いには住宅が建ち並ぶ.こうした路地を横に見ながら階段を上り終え,後ろを振り向くと写真6のような風景が目の前に広がる.写真6の風景は写真3の風景と異なる.階段を上るにつれて,眼下に広がる街並みも変化して見える.こうした坂道の風景の変化を楽しむことが,坂のまち長崎の醍醐味ではないだろうか.
既述したように,敷地は原則的に幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない.ところが,十人町の多くの敷地はこの要件を満たしていない.幅員4m以上という要件は,防災上と衛生上の観点から課されているものである.特に,幅員4m以上を確保する防災上の理由として,消防車の通行と延焼防止がある.では,十人町において,幅員4m以上という要件は現実的な要件なのだろうか.平地が限られた長崎市内において,住宅地は斜面に広がった.急勾配の道ゆえ,階段の設置を回避することは困難であったと推察できる.階段の存在は消防車の通行を困難にする.ゆえに,仮に幅員4m以上に拡幅する理由として消防車の通行を挙げることは,階段をなくさない限り現実的ではない.また,幅員4m以上に拡幅するもう一つの理由として延焼防止が挙げられるものの,物理的に延焼を防止する手段は幅員4m以上に拡幅することだけでない.沿道の建物を耐火造にすれば,延焼を防ぐことは可能である.問題は,耐火造化することが幅員4m以上に拡幅することの代替手段になりうるかどうかであろう.
十人町のように,物理的に幅員4m以上に拡幅することが困難であれば,既述した「3項道路」に指定することが可能である.さらに,2004年以降「3項道路」の適用範囲は広がった.趣きのある佇まいや歴史を有する幅員4m未満の2項道路においても「3項道路」に指定することが可能である.十人町をはじめとする坂のまち長崎の魅力を高めている要因の一部には,幅員の狭さや沿道の景観が含まれると考えられる.沿道の景観は,長い年月をかけて形成されたものであり,長い年月が景観に歴史と趣きを与えてきた.問題は,こうした要因を定性的に議論するだけでなく,客観的に評価しその真偽を明確にすることである.残念ながら,客観的に評価する方法は確立されていない.そんな中,「3項道路」の適用実績が多い斜面都市長崎は,趣きのある佇まいや歴史の保全と防災対策の両立を如何に図るか,そして両者の関係を定量的に評価するための手がかりを与えてくれるだろう.
 写真3
写真3
 写真4
写真4
 写真5
写真5
 写真6
写真6