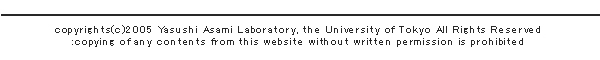トビリシ〜谷地に刻まれた歴史〜
今回はコーカサス地方・ジョージアの首都トリビシを取り上げたいと思います。
皆さんコーカサスのジョージアという国の場所を皆さんご存じでしょうか?日本では、某飲食チェーン店にてシュクメルリというジョージア料理が提供され話題となるなど、名前をご存じの方も多いのではないかと思います。コーカサスとは黒海とアラル海に挟まれたコーカサス山脈周辺地域を指し、その中でもジョージアは黒海に接する図1に位置する国です。

図1 ジョージア トリビシ 位置図(open street map 一部著者加工)
トリビシはジョージアの首都であり、現在の人口は120万人で、ジョージア全体の3分の1を占めています。近年はヨーロッパへの移住も増えているようで、首都トビリシの人口はほとんど増加していないようです。
トビリシの都市としての歴史は15世紀前にさかのぼります。当時この周辺を治めていた王様がシカがこの地の温泉で傷を癒したのを目撃して、都市の建設を決めたのが始まりといわれており、「トビリシ」という名前も現地語の「温かい」という言葉からきていると言われています。現在も旧市街には、スパがあり現地の人は浴場やサウナを楽しんでいました。トビリシは古くからペルシャ人、モンゴル人、ロシア人などに侵略された歴史や、シルクロードによる東西交流の経由地として発展した等、様々な文化が交じり合あったトリビシを今回紹介いたします。
都市の骨格
トビリシ市内にはクラ川が流れており、都市を囲む丘とともに都市景観を創出するとともに、都市の骨格となっています。図1のように市街地は南北を貫くクラ川沿いに集積して南北に広がっており、幹線道路や地下鉄、バス網もクラ川に沿う形で形成されています。市街地の幅は最も狭いところでは5㎞ほどしかありません。また、市街地が広がっているエリアもクラ川に向けて勾配があり、谷地にある街といえます。

図2 トビリシの地図(OpenStreetMap より)
市街地の南部にはランドマークとなるような教会や橋があり、観光スポットが集積しており、観光地としての色合いが強い街並みが続いています。写真1は市街地の南部の丘の上にあるナリカラ砦から、市街地を見下ろすと川岸の崖やその奥に広がる丘陵を感じていただけると思います。ナリカラ砦周辺のこのエリアは観光客が多くいるエリアで、ロシア人やヨーロッパ系の外国人や、地理的に近いためか中東系の観光客も多くいました。

写真1 ナリカラ砦近くから旧市街地を見下ろす。
一方北部は、写真2のように築年数の経過した集合住宅や、近年建設されたと思われる高層マンション・ビルなどが点在する住宅街が谷地に細長く広がっています。背の低い観光色の強い建物の多い観光スポット周辺とは対照的に、住宅団地やマンションなど容積の大きい建物も多くありました。

写真2 住宅地の街並み
都市内の交通
バスはトリビシの主要な公共交通機関で一般的なバスに加えて、需要に応じて連結バス、ミニバスも運行しています。地下鉄やバス、ミニバスに至るまで、現地の交通カードが利用でき、VISA、Master、AMEXなどの各種クレジットカードでの支払いにも対応しています。ミニバスは中型のバンを改造したようなもので、そこにもキャッシュレス決済用の端末が備え付けてあり、バスは主要な交通機関として整備されている印象でした。また、バスの車内にはバスの位置情報を示すディスプレイがあり、今どこのバス停に向かっているのかが人目でわかるようになっていて、なれない乗客にも配慮されているよいシステムだと感じました。バス停にも簡易的な電光掲示板があり、あと何分でどの路線のバスが来るのかが表示されていて、非常にわかりやすかったです。バスの遅延性を補うシステムが構築されていると感じました。

写真3 市内バス・バス停
トビリシのもう1つの主要な公共交通機関は地下鉄です。トビリシの地下鉄はソ連時代にモスクワ、サンクトペテルブルク、キエフの次に4番目に建設された歴史ある地下鉄となっています。路線は図3のように赤色のline1がクラ川に沿って、市街地を南北に横断しており、緑色のline2が西側に少し広がる住宅街に伸びています。地下鉄自体はカバーする範囲が限られているといえます。
しかし、市内の交通はバスと地下鉄の乗換は1回までで90分以内なら1回分の運賃(1ジョージアラリ=約50円)で移動することができることから、利用客数はバスをわずかに上回ってるようです。

図3 地下鉄路線図(Tbilisi Transport Plan 2023 - 2043より)

写真4 地下鉄プラットフォーム
また、市街西部の丘の上に位置するナリカラ砦やムタツミンダ公園への移動のためにロープウェイが整備されていますが、丘の上の終着点は観光地や遊園地、展望台なので、交通機関というよりは、主に観光需要に応えるものとなっています。一方で、歩いて上ると、30分ほど階段を上ることになるので、子供連れの家族や高齢の方などが観光するには必須のモビリティだと感じました。
観光資源
市内にはキリスト教の教会、古代の砦など歴史的な観光資源が豊富に存在しています。特にそうした観光資源が集中している市内南部では、旧市街の雰囲気を感じられる建物が集積しています。

図4 市街地南部 観光資源集積エリア地図(Open Street Mapを加工)
以下、特徴的な3つの観光スポットを紹介しようと思います。
メテヒ教会(写真5)は川岸の崖の上にあるシンボリックな教会です。トビリシが建設された5世紀にすでにあったようで、異民族の支配による破壊と修復を繰り返してきた歴史を持つものです。ジョージアの人々の民族的なアイデンティティにも資する教会であろうと思われます。

写真5 メテヒ教会
もう1つの象徴的な観光資源は同時代に建設されたとされるナリカラ砦です。急傾斜の丘の上に立っており、現存する砦は16?17世紀のものだそうですが、1500年近くこの丘の上からトビリシの街を見守ってきた要塞となっています。眺めがよいことから多くの人がロープウェイで丘の上まで上っていました。写真1のようにトリビシ南部の市街地の広い範囲を見渡すことができ、ナリカラ砦の麓は峠のようにクラ川の低地が狭く、軍事的に非常に戦略的な場所に立っていることがよくわかりました。

写真6 ナリカラ砦
トビリシは歴史的にはトルコ系の民族に支配されていた時代もあり、そうした時代からの影響を感じさせるのが、トビリシ唯一のイスラム教会であるジュマモスクです。今では街並みはソ連の時代を経て、このモスクさえ完全に西欧的な雰囲気の街並みとなっていますが、こうした施設がトビリシの多様な歴史を感じさせます。

写真7 ジュマモスク
市街地のまちの様子
トビリシの中心部に位置するルスタヴェリ通りは、トビリシの活気と歴史を象徴する目抜き通りです。写真8が示すように、この通りにはショッピングモールや多様なショップ、ホテルが軒を連ね、同時にジョージアの政治の中枢である国会議事堂、文化の中心地である美術館や歌劇場なども点在しています。この通りは、日常の賑わいと歴史的建造物が融合した独特の景観を作り出しています。
しかし、この通りの歩行者にとっての課題も感じました。6車線もの広い車道を持つこの通りは、トビリシの主要な幹線道路の一つであり、その交通量の多さから、地上に横断歩道はほとんど設けられていませんでした。そのため、歩行者は通りを横断するために、地下に設置された複数のアンダーパスを利用するしかありません。多くの人々が行き交い、多くの重要な施設のある通りであるだけに、歩行者の安全性と利便性を考慮した、地上の横断歩道や交差点の設置が望まれると感じました。

写真8 ルスタヴェリ通り
傾斜の大きい地域にも住宅が多く存在しており、日本の長崎、横須賀などの町に代表されるような谷戸空間と似た住宅地も見られました。こうした斜面住宅地を歩いていると、地元のおばあちゃんに荷物をもって一緒に上るように頼まれて一緒に上りましたが、急な階段が数百段上るような道で高齢の方には大変な道となっていました。

写真9 尾根から谷戸の斜面住宅を眺める
まとめ
傾斜地における住宅街は日本でも長崎や横須賀などにみられ、高齢住民のモビリティの問題となっています。トビリシはまだそうした段階にないかもしれませんが将来の課題となる可能性があります。 また、谷地に細長く形成された市街地は道路拡大余地が少ない点も懸念される点です。 クラ川はトリビシの都市の骨格となっており、谷の低地はほぼ幹線道路で占められています。観光客が多いエリアは横断歩道や歩行者天国の道路など、歩行者(観光客)を考慮した道路もありますが、それ以外の市街地では、貴重な平地が車優先の道路となっているように感じました。 ソ連解体後、堅調に成長を続けるジョージア経済を鑑みると、トリビシでも多くの都市が経験したように、市街地での交通渋滞の深刻化の問題に対応しなければならなくなるだろうと思われます。 現状でも、市内の貴重な平地の多くが道路に使用されており、平地に新たに道路を整備する余地はほとんどないと考えられるので、公共交通の整備・拡充や、利用拡大がこれからの課題になることが想定されます。 こうした懸念点もあるものの、谷地に形成された細い路地や谷戸に形成された住宅地や温泉地であることなど、日本の都市との共通点も多く、街並みは西欧風ではあるものの親しみのある街並みでした。 一方で、傾斜によって美しい景観が創出されており、平地部には、ランドマークとなる観光資源やレストラン、ホテル、住宅が高密度で存在するなど、こうした地形がトリビシの魅力を長い時間をかけて形成していると感じました。

写真10 クラ川沿いの幹線道路
参考資料
- [1]Soviet Architecture in Tbilisi: 20 Iconic & Striking Sights(https://www.redfedoradiary.com/soviet-architecture-in-tbilisi-georgia/)
- [2] open street map(hhttps://www.openstreetmap.org/#map=11/41.7231/44.7988)
- [3] Wikipedia tbilisi (https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98)
- [4] 日本ジョージア商工会議所(https://jgcci.org/)
- [5] 経産省 令和3年 ジョージア国・トビリシ地下鉄車両調達事業計画調査(https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000216.pdf)
- [6] トビリシの交通計画(Tbilisi Transport Plan 2023 - 2043)(https://tbilisi.gov.ge/img/original/2023/8/17/Broshura-PDF.pdf?fbclid=IwAR0rsx45iMQiz54_vVA4wob8jWfS4070I0DCPRDkQ0uxBu2Aajmd4iRguTs)
(文責・写真撮影:姫野楓)
まちなみ探訪
>> HOME