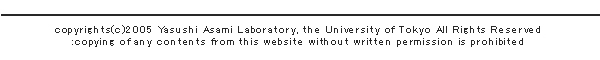大山祇神社参道を歩く 今治市大三島町
しまなみ海道と大山祇神社
大三島は愛媛県今治市に属する芸予諸島のひとつで、愛媛県では最大の人口約5000人の島です。2005年までは島の東西で2町に分かれていましたが、いわゆる平成の大合併により今治市の一部となりました。西瀬戸自動車道(しまなみ海道)が通り、四国側の伯方島とは大三島橋、本州側の生口島とは多々羅大橋で結ばれています。 その大三島を「神の島」と呼ばしめるのが大山祇神社です(写真1)。日本総鎮守と呼ばれ、全国に一万社あまりの分社を持つ神社です。境内中央には樹齢約2,600年の神木である大楠が鎮座しており、神社内の楠(クスノキ)群は日本最古の原始林社叢の楠群として、昭和26年に国の天然記念物に指定されています。室町初期に再建された三間社流造り(さんげんしゃながれづくり)の本殿、切妻造りの拝殿も国指定重要文化財です。 大山祇神社の正面にある「お食事処 大漁」は格安で魚介料理が食べられる人気店で、いつも行列ができています(写真2)。開店前に到着した私は、店の前に置かれた予約表に名前を書いて大山祇神社を参拝しつつ、11時半の開店と同時に入店しました。980円の海鮮丼をいただいたあと、女将さんに「島内に古い町並みが残っているところはありませんか」と聞いたところ、女将さんは私と一緒に店外に出て指で方向を示しながら、「いちおうこっちが参道だけど、何も無いからがっかりすると思うよ」と笑いながら、次の客を店内に招き入れました。

1.大山祇神社

2.お食事処・大漁
大山祇神社参道を歩く
神社を背に石畳が整備された参道を歩くと旅館がいくつか目に入ります。写真3の料理旅館「茶梅」は、5代にわたり島の味を守る老舗だそうです。古い建物を活用した店舗も見られました。旧法務局を活用した「大三島みんなの家」(旧法務局)は、カフェ・ワインバルとして営業しています(写真4)。プリツカー賞建築家の伊東豊雄さんが、「日本一美しい島・大三島をつくろうプロジェクト」の一環で、伊藤建築塾の塾生や地元住民らとリノベーションした建物です(なお、島内には伊東豊雄建築ミュージアムもあります)。 大三島ブリュワリーは、島の特産である柑橘を使用したフルーティーな地ビールの醸造所です(写真5)。「大三島にご来島頂き、大三島滞在の想い出とともに味わって頂きたい」というコンセプトから通信販売はしていないそうなので、大山祇神社を訪れる際にぜひ味わってください。 で新幹線を利用し、そこから徒歩で移動するという方法である。新富士駅は新幹線こだま号が停車する鉄道駅で、東京駅から1時間強の移動で到着することができる。新幹線によって静岡県を通過する際には、北側に富士山の絶景を見られることは、新幹線を利用したことがある方ならご存知だろう。新富士駅に降り立つと、その絶景をより十分に堪能することができる。私が今回富士市に訪れた日はあいにく天候に恵まれず、富士山を見ることができなかったが、天候が良い日は富士山がとても美しく見える(図3)。今回の訪問に限らず私は富士市に何度か訪れたことがあるが、訪れる度に富士山の荘厳さに圧倒される。ただし、富士市から見える富士山のそばには、工場群から立ち上る排気ガスがセットで目に映る。先述のように、富士市は製紙工場が数多く立地している。排気ガスの存在は製紙工場がしっかり稼働している様子を示してくれる。富士山の絶景スポットは多くあれど、その排気ガスが上空に立ち上る様子とセットで富士山を拝むことができるのは、富士市ならではと言っても過言ではないだろう。今回私が訪れた際の写真は図4であり、富士山は雲に隠されてその全貌を見ることはできなかったが、排気ガスが様々な場所で上空に立ち上る様子はしっかりと確認することができた。

3.料理旅館・茶梅

4.大三島みんなの家

5.大三島ブリュワリー
失われる歴史的建物
しかし、大漁の女将さんが言っていた通り、参道は全体的にさびれた雰囲気でした。写真6の建物は「石田の風呂屋」と呼ばれる銭湯だったそうです(参道入口に置かれた案内図より)。写真7の「鈴木薬舗」は築百年を超える、参道沿いで現存する最も古い建物だそうですが、いまにも崩れ落ちそうで、屋根から外された瓦が道路脇に積み上げられていました。参道入口を示すゲートも「レトロ感」というより寂しさを漂わせるものでした(写真8)。道路脇で何か作業をしていた高齢男性に話しかけると、「舟が参拝の交通手段だった頃は栄えていたが、時代が変わったから仕方ない」とのことでした。かつて参拝者は、宮浦港にある「一の鳥居」をくぐって、この参道を経て神社を訪れていたそうです。モータリゼーションが進んで、神社すらも「隣接する民地を買って駐車場にした」ほどなので、参道の復権に向けた道のりは険しいと感じました。

6.石田の風呂屋

7.鈴木薬舗

8.参道入口を示すゲート
一の鳥居へ
高齢男性の話を受けて、宮浦港にある一の鳥居を訪れました(写真9,10)。周辺には市役所の大三島支所や図書館、商工会の建物などがあり、旧町の中心地であったことが伺えます。一の鳥居は創建当時、日本一の高さだったそうです。かつて、宮浦港に到着した参拝客は、「一の鳥居」をくぐり、100軒以上も店舗が並ぶ参道で買い物や飲食を楽しみながら、「二の鳥居」(前掲写真1)まで歩いたのでしょう。地図に示す通り、宮浦港から神社に至るこのルートは県道21号線に2度分断されています。一の鳥居から参道入口のゲート(前掲写真8)に至る御串山(みくしやま、大山祇神社の飛地境内)の崖地沿いの区間に、往時の面影は全く残っていません。県道21号は神社の正面で再びこのルートにぶつかり、二の鳥居の写真を撮ろうとする人と自動車が交錯する場面を何度も目撃しました。本来は一の鳥居から入って参拝すべきだと思いつつも、1km弱の道のりを歩いてもらうのは厳しいだろうと感じる猛暑日の探訪でした。

9.一の鳥居

10.宮浦港の桟橋より海を望む

探訪ルートの地図。丸数字は写真のおおよその位置を表す (? OpenStreetMap contributors)
参考資料
- [1]大山祇神社ホームページ「大山祇神社について」(hhttps://oomishimagu.jp/about/)
- [2] 今治市ホームページ「大山祇神社」(hhttps://www.city.imabari.ehime.jp/kanko/spot/?a=226)
- [3] 今治建築WEB「大三島みんなの家」 (https://www.oideya.gr.jp/kenchiku/chapter/omishima/03_1.html)
- [4] 大三島ブリュワリー (hhttps://www.omishima.beer/)
(文責・写真撮影:樋野公宏)
まちなみ探訪
>> HOME