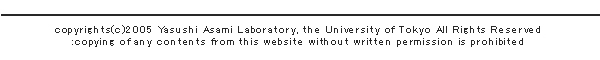四方津・猿橋
◆四方津
新宿駅からJR中央本線甲府方面の下り列車に揺られること70分、山梨県に入り、幾度かトンネルを抜けた山間に、
天上へと通じるかのような二つの開発戸建住宅地―コモアしおつ、パストラルびゅう桂台―があります。
駅前から住宅街の玄関口へと通じる乗り物でも比較的有名な二つの住宅地は、90年代に入ってから分譲が始まり、
10年以上の年月を経て、それぞれが魅力のある景観を生み出す試みを続けています。一見、特異にも見える郊外で
の生活に特化したこれらのコミュニティの中で、どのような理念とプロセスをもって町並みが形成されているのでしょうか。
■四方津
山梨県北都留郡上野原市の西部に広がる『コモアしおつ』。事業名が町名にも用いられており、1991年の分譲開始以来、
四つの戸建住宅エリアに分けられた開発が行われています。開発総面積80ha、総戸数1610戸、計画人口約6000人の事業計画に対し、
現在総戸数1121戸、人口3419人からなり、200㎡台の宅地を中心に分譲が行われているようです。
ここで、戸数の増加に対して人口の増加が小さい理由(1121/1610 > 3419/6000ということ)を考えると、入居する世帯の人員数と
平均世帯人員数の変動に対する予測に誤差があったといえます。
また、1988年の平均世帯人員が3.10人であったのに対し、事業の計画段階では3.73人(=6000人/1610戸)の世帯人員を想定しており、
二世代から三世代の家族向けの事業であることが数値の上からも分かります。ちなみに、2006年の平均世帯人員2.65人に対し、
3.05人(=3419人/1121戸)の世帯人員を実現しているようです。(以上の統計値は、厚生労働省『平成18年 国民生活基礎調査の概況 』
より・・・*1)
時として、ニュータウンの世代構成の偏りがコミュニティの持続的な発展に影響を及ぼしますが、コモアしおつでも中長期的な課題
として挙げられるでしょう。
分譲から16年経つコモアしおつ1丁目付近は路地や植栽の手入れも行き届いており、異国の郊外住宅地を思わせる風景を形成しています
(写真1)。一方で、現在開発が進められているコモアしおつ4丁目トリコパルクでは、住宅と周辺環境の関係に対するいくつかの提案
(外観の見え方、住棟間のオープンスペース、室内からの見通し等)が行われ、リズミカルな風景を形成しています(写真2)。
 (写真1)コモアしおつ1丁目
(写真1)コモアしおつ1丁目
 (写真2)コモアしおつ4丁目トリコパルク
(写真2)コモアしおつ4丁目トリコパルク
街区に目を向けると、曲線状の街路と遊歩道、四つの公園の配置は、歩行者に対する配慮が行われ、街全体の分かりやすさにも
寄与しています。
例えば、曲線状の街路には楓の木が植えられ(写真3)、マンホールには楓の葉のモチーフ(写真4)、敷地内東部の石の公園にはト
ーテムポール(トーテムポールはバンクーバー市内のスタンレーパークの観光スポットのひとつ)があるように、カナダを連想さ
せるイメージがちりばめられているのも住人を楽しませるアイキャンディとなっているようです。このような分かりやすいイメー
ジは時としてキッチュなものになりがちですが、ここでは街の親しみやすさに寄与する好事例となっています。
 (写真3)外周道路の楓
(写真3)外周道路の楓
 (写真4)遊歩道とマンホール
(写真4)遊歩道とマンホール
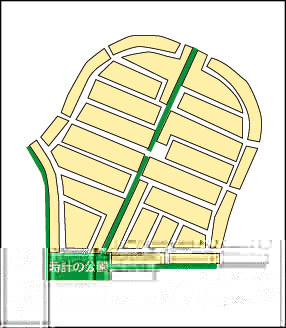 (図1)コモアしおつ1丁目の街区と遊歩道
(図1)コモアしおつ1丁目の街区と遊歩道
コモアしおつでは、住宅地としての環境を維持増進することを目的に、敷地、構造、用途、形態、意匠に関する基準について
「建築協定」として協定を行い、各所で注意を呼びかけています(写真5)。外壁の色彩については、豊かな緑を大事にすると共に
、緑の中の住宅を美しく見せる色、落ち着きのある家並みを作るのに適した色を外部の専門機関に委託してガイドラインを作
成しています。建替え、リフォーム、カーポート・フェンス等の設置には『コモアしおつ管理組合』への事前の届出を必要と
しており、住みやすい豊かな街づくりに対して住民一人ひとりが協調するように促しています(*2)。今日の一部の都市では隣
人関係の希薄さやコミュニティの脆弱さが指摘される中、景観形成に関する市民間の対話はコミュニティの結束力を高めるひ
とつの方向性を示しているように思われます。外部の専門機関に頼るだけでなく、専門家を交えて美しさや調和に関する対話
を重ねることが、特色ある景観を生み出す上で必要だと思います。
 (写真5)風景の一部になる建築協定
(写真5)風景の一部になる建築協定
日本の住宅市場の特徴は、欧米の先進国と比較して、高価格、短い寿命、中古流通市場の未発達だと言われています。
コモアしおつのような着工から20年も経たない住宅地の住宅寿命は、全国的な水準よりも長いものだと考えられます。
建築協定を守ることで保たれる町並みの調和は、入居者の世代交代と中古住宅の流通を経て、後の世代にどのような景観を
もたらすのでしょうか。
■猿橋(山梨県大月市猿橋町桂台の分譲住宅地)
日本三奇橋のうちのひとつに数えられる猿橋は、山梨県大月市にあります。崖の両岸から突き出された角材の上に橋桁がのっ
ている構造で610年頃築かれたと言われていますが、現在のものは1984年に再架されたもので、高さ31m、幅3.3m、長さ30.9mあります。
 (写真6)日本三奇橋『猿橋』
(写真6)日本三奇橋『猿橋』
 (写真7)猿橋の意匠を取り入れた駅舎。駅舎の向こうに見えるのが、シャトル桂台。
(写真7)猿橋の意匠を取り入れた駅舎。駅舎の向こうに見えるのが、シャトル桂台。
JR中央本線猿橋駅に隣接した山地を造成して造られたパストラルびゅう桂台は、猿橋駅から送迎タクシーに乗って五分程のところ
に位置し、四方を残地森林と法面に囲まれ、プロムナードと迂回路との組み合わせが特徴的な街区をした閑静な土地にありました。
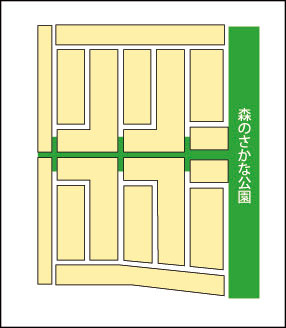 (図2)桂台2丁目の街区
(図2)桂台2丁目の街区
住宅街を南北に縦断する歩行者専用路と交差する森のさかな公園は、近辺に生息するニホンリスの回廊としての機能も意図されている
そうです。森の中に突如として現れる魚のオブジェと開発が進んでいない桂台3丁目-4丁目の風景とも相俟って、不思議な雰囲気を持っ
た公園となっています(写真8)。
森のさかな公園以南の宅地開発はストップしていますが、電柱が立ち並び、インフラの整備は済んでいるようです(写真9)。
 (写真8)森のさかな公園のオブジェ
(写真8)森のさかな公園のオブジェ
 (写真9)桂台3丁目付近の風景
(写真9)桂台3丁目付近の風景
開発が停滞している理由のひとつには、当初想定していた住民の交通手段が十分に機能しなかったことが考えられます。
活気のある街づくりを行うためには、新たな輸送方式の提案と同様に、雑草に侵食された歩道の整備や電線類の地中化など、開発事業者
と住民が協同して地域の特色を活かした新しい町並みを生み出す試みを継続することが必要だと思います。森のさかな公園以南の開発が
進んでいない地域は電柱の地中化に対する障壁も少ないと考えられ、自然と住宅地の調和のとれた景観の提案が行われると面白いかもし
れません。
住宅団地の事業主体は2007年7月18日までにシャトル桂台の運行再開の断念を発表しており、今後新たな輸送方式が検討されるそうです。
地形的な問題から代替手段は限られてくるかもしれませんが、猿橋の眺望も楽しむことのできる魅力的な解決方法に期待したいと思います。
なお同団地には現在、開発当初の計画の開発面積73.8ha、総戸数1000戸、計画人口3,500人に対し、322世帯、1000人が居住しており(*3)、
運行停止後はシャトル桂台の管理会社が配備したタクシーやバスで住民を代行輸送しています。
地域生態系の保全と宅地造成の双方を矛盾することなく両立させ、住環境を整備していくことは多くの困難を伴います。
大月市猿橋町桂台では、地域生態系の状態を把握するための指標となる環境指標生物にニホンリスを選定し、ニホンリスの保全対策を
行うことで、生態系全体の保全を評価しようとする試みを行っているそうです。(*4)
環境指標生物とは、様々な環境条件を調べるために、その環境に生息する生物のうち、ある環境条件に敏感な生物を指して用いられる
言葉です。例えば、河川の汚濁を調べるために、メダカや鮎の生態を調べる事例が比較的有名かもしれません。
ある環境条件を知るために、例えば温度や湿度、化学組成などを直接調べずに、環境指標動物を用いる利点は、
・特別な機器を必要とせず、誰にでも測定ができること
・時間的、地理的な厳密さを必要としないこと
・原因が特定できなくても、環境の悪化を知ることができること
などがあります。私たちも、ゴキブリや蟻、カラス、カビといった生物を、住環境を評価するための指標として日常的に利用しているの
ではないでしょうか。
大月市桂台の場合、数ある生物の中からリスを環境指標動物に選んだ理由は、ニホンリスが希少動物であることと同時に、地域生態系
の保全と良好な住宅地環境の創出といった観点から、リスが人間にとって親しみやすく、継続的な環境保全、創出活動のために関係者
の合意形成や住宅地のイメージづくりに寄与することが想定されています。(*5,*6)
近年、たびたび耳にすることがある循環型の環境を構築するためには、生態系の多様性をどのように確保するかということが大きな
指標となります。
希少種や人間にとって好ましい生き物を保護することが、生態系の多様性を確保する活動かどうかということについては検証が必要だ
と思いますが、人間の活動(住宅地開発、外来植物の持ち込み・・・)が地域固有の生態系にどのような影響を与えるのかを、環境指標動物
を通して知ることは、近代的な生活の中で自然との共生を実感できる大切な機会だと思います。
今回の調査では、残念ながらニホンリスを目にすることは出来ませんでしたが、庭先から溢れ出る果樹の匂いに誘われ出てくる昆虫を
数多く目にすることが出来、豊かな自然と落ち着いた生活を求めてきた入居者の住まいに対する思いを庭先に垣間見た気がしました(写真10)。
(写真・文責:引田有人)
 (写真10)プロムナードの様子
(写真10)プロムナードの様子
参考文献:
(1)
厚生労働省大臣官房統計情報局『平成18年 国民生活基礎調査の概況 』
(2)
コモアしおつ公式サイト/コモアの風/コモアしおつ建築協定について
(3)
『山梨日日新聞web版』2007年07月19日(木)「大月の小型モノレール 運行再開断念」
(2007/08/05アクセス)
(4)
「ニホンリスを環境指標に、大規模造成工事で地域生態系を保全~リスの行動範囲や移動経路を調査し、各種保全策を展開~」
(2007/08/05アクセス)
(5)
中村健二他(2001)「環境指標動物を用いた地域生態系保―パストラルびゅう桂台におけるニホンリスの保全―」『清水建設研究報告』
(6)
米村惣太郎他(2007)「環境指標動物を用いた地域生態系保全(その2)-その後のリスの橋と利用状況および生息環境について-」
『清水建設研究報告』
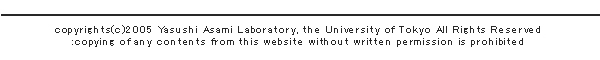
まちなみ探訪
>> HOME
 (写真2)コモアしおつ4丁目トリコパルク
(写真2)コモアしおつ4丁目トリコパルク
街区に目を向けると、曲線状の街路と遊歩道、四つの公園の配置は、歩行者に対する配慮が行われ、街全体の分かりやすさにも 寄与しています。
例えば、曲線状の街路には楓の木が植えられ(写真3)、マンホールには楓の葉のモチーフ(写真4)、敷地内東部の石の公園にはト ーテムポール(トーテムポールはバンクーバー市内のスタンレーパークの観光スポットのひとつ)があるように、カナダを連想さ せるイメージがちりばめられているのも住人を楽しませるアイキャンディとなっているようです。このような分かりやすいイメー ジは時としてキッチュなものになりがちですが、ここでは街の親しみやすさに寄与する好事例となっています。
 (写真3)外周道路の楓
(写真3)外周道路の楓
 (写真4)遊歩道とマンホール
(写真4)遊歩道とマンホール
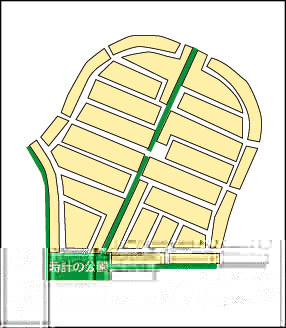 (図1)コモアしおつ1丁目の街区と遊歩道
(図1)コモアしおつ1丁目の街区と遊歩道
コモアしおつでは、住宅地としての環境を維持増進することを目的に、敷地、構造、用途、形態、意匠に関する基準について 「建築協定」として協定を行い、各所で注意を呼びかけています(写真5)。外壁の色彩については、豊かな緑を大事にすると共に 、緑の中の住宅を美しく見せる色、落ち着きのある家並みを作るのに適した色を外部の専門機関に委託してガイドラインを作 成しています。建替え、リフォーム、カーポート・フェンス等の設置には『コモアしおつ管理組合』への事前の届出を必要と しており、住みやすい豊かな街づくりに対して住民一人ひとりが協調するように促しています(*2)。今日の一部の都市では隣 人関係の希薄さやコミュニティの脆弱さが指摘される中、景観形成に関する市民間の対話はコミュニティの結束力を高めるひ とつの方向性を示しているように思われます。外部の専門機関に頼るだけでなく、専門家を交えて美しさや調和に関する対話 を重ねることが、特色ある景観を生み出す上で必要だと思います。
 (写真5)風景の一部になる建築協定
(写真5)風景の一部になる建築協定
日本の住宅市場の特徴は、欧米の先進国と比較して、高価格、短い寿命、中古流通市場の未発達だと言われています。 コモアしおつのような着工から20年も経たない住宅地の住宅寿命は、全国的な水準よりも長いものだと考えられます。 建築協定を守ることで保たれる町並みの調和は、入居者の世代交代と中古住宅の流通を経て、後の世代にどのような景観を もたらすのでしょうか。
■猿橋(山梨県大月市猿橋町桂台の分譲住宅地)
日本三奇橋のうちのひとつに数えられる猿橋は、山梨県大月市にあります。崖の両岸から突き出された角材の上に橋桁がのっ ている構造で610年頃築かれたと言われていますが、現在のものは1984年に再架されたもので、高さ31m、幅3.3m、長さ30.9mあります。
 (写真6)日本三奇橋『猿橋』
(写真6)日本三奇橋『猿橋』
 (写真7)猿橋の意匠を取り入れた駅舎。駅舎の向こうに見えるのが、シャトル桂台。
(写真7)猿橋の意匠を取り入れた駅舎。駅舎の向こうに見えるのが、シャトル桂台。
JR中央本線猿橋駅に隣接した山地を造成して造られたパストラルびゅう桂台は、猿橋駅から送迎タクシーに乗って五分程のところ に位置し、四方を残地森林と法面に囲まれ、プロムナードと迂回路との組み合わせが特徴的な街区をした閑静な土地にありました。
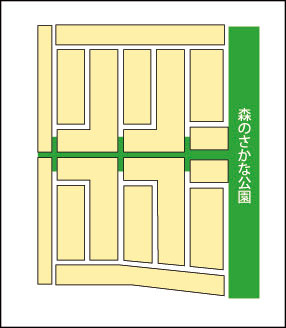 (図2)桂台2丁目の街区
(図2)桂台2丁目の街区
住宅街を南北に縦断する歩行者専用路と交差する森のさかな公園は、近辺に生息するニホンリスの回廊としての機能も意図されている そうです。森の中に突如として現れる魚のオブジェと開発が進んでいない桂台3丁目-4丁目の風景とも相俟って、不思議な雰囲気を持っ た公園となっています(写真8)。
森のさかな公園以南の宅地開発はストップしていますが、電柱が立ち並び、インフラの整備は済んでいるようです(写真9)。
 (写真8)森のさかな公園のオブジェ
(写真8)森のさかな公園のオブジェ
 (写真9)桂台3丁目付近の風景
(写真9)桂台3丁目付近の風景
開発が停滞している理由のひとつには、当初想定していた住民の交通手段が十分に機能しなかったことが考えられます。
活気のある街づくりを行うためには、新たな輸送方式の提案と同様に、雑草に侵食された歩道の整備や電線類の地中化など、開発事業者 と住民が協同して地域の特色を活かした新しい町並みを生み出す試みを継続することが必要だと思います。森のさかな公園以南の開発が 進んでいない地域は電柱の地中化に対する障壁も少ないと考えられ、自然と住宅地の調和のとれた景観の提案が行われると面白いかもし れません。
住宅団地の事業主体は2007年7月18日までにシャトル桂台の運行再開の断念を発表しており、今後新たな輸送方式が検討されるそうです。 地形的な問題から代替手段は限られてくるかもしれませんが、猿橋の眺望も楽しむことのできる魅力的な解決方法に期待したいと思います。
なお同団地には現在、開発当初の計画の開発面積73.8ha、総戸数1000戸、計画人口3,500人に対し、322世帯、1000人が居住しており(*3)、 運行停止後はシャトル桂台の管理会社が配備したタクシーやバスで住民を代行輸送しています。
地域生態系の保全と宅地造成の双方を矛盾することなく両立させ、住環境を整備していくことは多くの困難を伴います。
大月市猿橋町桂台では、地域生態系の状態を把握するための指標となる環境指標生物にニホンリスを選定し、ニホンリスの保全対策を 行うことで、生態系全体の保全を評価しようとする試みを行っているそうです。(*4)
環境指標生物とは、様々な環境条件を調べるために、その環境に生息する生物のうち、ある環境条件に敏感な生物を指して用いられる 言葉です。例えば、河川の汚濁を調べるために、メダカや鮎の生態を調べる事例が比較的有名かもしれません。
ある環境条件を知るために、例えば温度や湿度、化学組成などを直接調べずに、環境指標動物を用いる利点は、
・特別な機器を必要とせず、誰にでも測定ができること
・時間的、地理的な厳密さを必要としないこと
・原因が特定できなくても、環境の悪化を知ることができること
などがあります。私たちも、ゴキブリや蟻、カラス、カビといった生物を、住環境を評価するための指標として日常的に利用しているの ではないでしょうか。
大月市桂台の場合、数ある生物の中からリスを環境指標動物に選んだ理由は、ニホンリスが希少動物であることと同時に、地域生態系 の保全と良好な住宅地環境の創出といった観点から、リスが人間にとって親しみやすく、継続的な環境保全、創出活動のために関係者 の合意形成や住宅地のイメージづくりに寄与することが想定されています。(*5,*6)
近年、たびたび耳にすることがある循環型の環境を構築するためには、生態系の多様性をどのように確保するかということが大きな 指標となります。
希少種や人間にとって好ましい生き物を保護することが、生態系の多様性を確保する活動かどうかということについては検証が必要だ と思いますが、人間の活動(住宅地開発、外来植物の持ち込み・・・)が地域固有の生態系にどのような影響を与えるのかを、環境指標動物 を通して知ることは、近代的な生活の中で自然との共生を実感できる大切な機会だと思います。
今回の調査では、残念ながらニホンリスを目にすることは出来ませんでしたが、庭先から溢れ出る果樹の匂いに誘われ出てくる昆虫を 数多く目にすることが出来、豊かな自然と落ち着いた生活を求めてきた入居者の住まいに対する思いを庭先に垣間見た気がしました(写真10)。 (写真・文責:引田有人)
 (写真10)プロムナードの様子
(写真10)プロムナードの様子
参考文献:
(1)
厚生労働省大臣官房統計情報局『平成18年 国民生活基礎調査の概況 』
(2)
コモアしおつ公式サイト/コモアの風/コモアしおつ建築協定について
(3)
『山梨日日新聞web版』2007年07月19日(木)「大月の小型モノレール 運行再開断念」
(4)
「ニホンリスを環境指標に、大規模造成工事で地域生態系を保全~リスの行動範囲や移動経路を調査し、各種保全策を展開~」
(5)
中村健二他(2001)「環境指標動物を用いた地域生態系保―パストラルびゅう桂台におけるニホンリスの保全―」『清水建設研究報告』
(6)
米村惣太郎他(2007)「環境指標動物を用いた地域生態系保全(その2)-その後のリスの橋と利用状況および生息環境について-」 『清水建設研究報告』