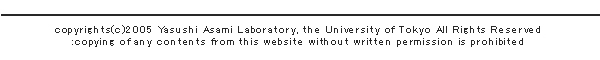「神の島」久高島―琉球開闢神話はじまりの地
◆久高島の概要
久高島は、沖縄県本島の東方約5kmに位置する周囲8km、人口223人(2024年6月末時点)のサンゴ礁に囲まれた小さく平坦な島です(写真1)。県南部の知念半島にある安座真港からは高速船で25分、フェリーで25分ほどです。
久高島は古くから「神の島」として知られます。その歴史は琉球王国の精神文化や信仰と深く結びついており、今もなお聖地として特別な尊厳を持つ場所です。
住宅は細長い島の南方に集中して集落を形成しています(図1)。南の端にはフェリーや高速船乗り場のある仁徳港、北の端にはアマミキヨが降り立ったといわれるハビャーン(写真2)があります。集落の道路は入り組んでいますが、それ以外は南北につながる長い道とそれらをつなげる東西の道が数本ずつあるだけです。
 写真1:斎場御嶽から臨む久高島
写真1:斎場御嶽から臨む久高島
 図1:久高ガイドマップ (出典:南城市久高島観光交流サイト)
図1:久高ガイドマップ (出典:南城市久高島観光交流サイト)

 写真2:ハビャーン(カベール岬)。植物群は国指定天然記念物
写真2:ハビャーン(カベール岬)。植物群は国指定天然記念物
◆琉球王国開闢(かいびゃく)神話
琉球王国開闢神話に出てくる女神アマミキヨと男神シネリキヨは、ニライカナイ(海の彼方にある神界)から久高島へ降り立ち、国造りを始めたとされています。最初に沖縄に7つの御嶽(うたき、祭祀を行う神聖な場所)が作られ、そのうち琉球王国で最も神聖なものとされる斎場(せーふぁ)御嶽は、本島から久高島を臨む位置関係にあります(前掲写真1)。このことも久高島が沖縄におけるニライカナイ信仰の重要な場所であることを示しています。久高島で最高の聖地は島の中央部にあるフボー御嶽(写真3)で、奥には祭祀場である円形広場がありますが、現在は立ち入り禁止になっています。
久高島の祭祀の中でもよく知られるのが「イザイホー」です。久高島で生まれ育った女性が神女になる儀式のことで、琉球王国時代から400年にわたり12年毎に行われてきました。『沖縄と色川大吉』(2021年)を読むと、当時の祭祀の様子が事細かく記されており、島の人々の行事に掛ける思いも伝わってきます。しかし、この祭祀は後継者不足により1978年を最後に行われていません。それでも、久高島には今も、沖縄のほとんどで消えかけた古来の祭祀組織が残っており、年間で約30回もの祭祀があります。祭祀の行われる場所は、フボー御嶽のほかに、ニライカナイから五穀の種が入った壺が流れ着いたというイシキ浜、外間(ふかま)ウプグィ、御殿庭(うどぅんみゃー)など島全体に点在しています。なかでも、かつて久高御殿があった御殿庭は12年毎のイザイホーが行われていた場所で、今でも村落の主要な年中祭祀の祭場となります(写真4)。なお、祭祀中は観光客が行動を制限されることがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
 写真3:フボー御嶽
写真3:フボー御嶽
 写真4:御殿庭。左奥のバンカイヤーという建物はイラブー(エラブウミヘビ)の燻製施設
写真4:御殿庭。左奥のバンカイヤーという建物はイラブー(エラブウミヘビ)の燻製施設
◆島のまちなみ
集落には琉球石灰岩を使った石垣や石畳、琉球赤瓦を使った屋根といった沖縄の伝統的なまちなみが見られます。石垣は、「野面(のづら)積み」といわれる自然の形のまま積み上げたものと、「相方(あいかた)積み」といわれる多角形に加工した石を互いにかみ合うように積み上げたものがあり、通りの印象に変化をもたらしています。また、沖縄の伝統的な建築様式の一つであるヒンプン(写真5)を設けている家も見られます。家の正面にある目隠し塀のことで、魔除けや風よけなどの役割もあります。
集落には山村留学を受け入れる「久高島留学センター」が2001年に開設されています。かつては久高小中学校に通う中学生がわずか2名まで減少するという統廃合の危機もありましたが、現在では全国各地の留学生を毎年10数名受け入れているそうです。

 写真5:相方積みの石垣とヒンプン(左)と野面積みの石垣(右)
写真5:相方積みの石垣とヒンプン(左)と野面積みの石垣(右)
◆土地総有制
久高島では、国有地や電力会社の用地を除き、「字久高」名義で土地を登記・所有する「土地総有制」がとられています。琉球王朝からの「地割制」が県内で唯一残る地域で、明治32年(1899年)に実施された沖縄県土地整理事業でも、土地の私的所有には移行せず、総有制を守り続けました。その後、土地の利用実態や管理方法の変遷を踏まえ、1989年に「土地憲章」が制定されました。それまでの慣習を整序し、新たな土地利用の発生を考慮して規範を刷新したものです。もちろん、居住地や農地も利用権を有するのみです。なお、土地所有主体である「字久高」の構成員は、おおむね自治会の久高区と重なっていますが、完全には一致しません。たとえば、久高区の住民であっても、構成員資格(3年の居住要件)を満たしていなければ「字久高」の構成員にはなりません。この「土地総有制」により、久高島はリゾート開発などの乱開発から守られてきたと言えます。
◆島民との思いがけない交流
島を一通り回り終えた夕暮れ時、海の見える港近くのベンチでゆんたく(おしゃべり、団らん)している3人の年配男性から「一緒に飲もう!」と声を掛けられました。島民と話す絶好の機会を逃すまいと応じたところ、オリオンビールに古酒(くーす)、手作りの料理までご馳走になり、島での暮らしやその変化について聞くことができました。薦められた食堂でイラブー汁を堪能した後、宿泊先の久高島宿泊交流館へ戻ると、入口横のテントに出現した「居酒屋てぇげぇぐゎー」(てぇげぇはテキトー、ぐゎーは小さなもの)から、今度は4人の年配男性に誘われました。久高島の方言を教えてもらったり、三線(さんしん)を弾かせてもらったり、素手でイラブ―(※有毒)を捕る方法を教えてもらったり、ヤシガニと星空を観るナイトツアーに連れて行ってもらったりと、想像もしていなかった楽しい時間を過ごすことができました(写真6)。
今回初めて訪れた久高島は、「神の島」という名前から想像していた張り詰めた空気感とは違って、優しい光に包まれた温かい雰囲気の島でした。私たちのように島に宿泊する人は多くありませんが、久高島には年間4万人を超える観光客が訪れています。観光振興が島の生活・文化の維持を妨げないこと、さらにはプラスの効果をもたらすことを切に願っています。
 写真6:ピザ浜から見た朝日
写真6:ピザ浜から見た朝日
(文責・写真:樋野公宏・綾美)
◆参考文献
・南城市ホームページ
・三木健編『沖縄と色川大吉』, 不二出版, 2021年
・小川竹一「久高島の土地総有制の意義」, 地域研究, 13, 195-212, 2014年
・比嘉康雄『日本人の魂の原郷 沖縄久高島』, 集英社新書, 2000年
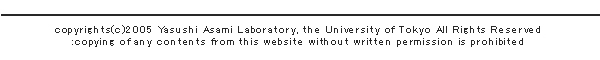
まちなみ探訪
>> HOME

図1:久高ガイドマップ (出典:南城市久高島観光交流サイト)




写真2:ハビャーン(カベール岬)。植物群は国指定天然記念物
◆琉球王国開闢(かいびゃく)神話
琉球王国開闢神話に出てくる女神アマミキヨと男神シネリキヨは、ニライカナイ(海の彼方にある神界)から久高島へ降り立ち、国造りを始めたとされています。最初に沖縄に7つの御嶽(うたき、祭祀を行う神聖な場所)が作られ、そのうち琉球王国で最も神聖なものとされる斎場(せーふぁ)御嶽は、本島から久高島を臨む位置関係にあります(前掲写真1)。このことも久高島が沖縄におけるニライカナイ信仰の重要な場所であることを示しています。久高島で最高の聖地は島の中央部にあるフボー御嶽(写真3)で、奥には祭祀場である円形広場がありますが、現在は立ち入り禁止になっています。
久高島の祭祀の中でもよく知られるのが「イザイホー」です。久高島で生まれ育った女性が神女になる儀式のことで、琉球王国時代から400年にわたり12年毎に行われてきました。『沖縄と色川大吉』(2021年)を読むと、当時の祭祀の様子が事細かく記されており、島の人々の行事に掛ける思いも伝わってきます。しかし、この祭祀は後継者不足により1978年を最後に行われていません。それでも、久高島には今も、沖縄のほとんどで消えかけた古来の祭祀組織が残っており、年間で約30回もの祭祀があります。祭祀の行われる場所は、フボー御嶽のほかに、ニライカナイから五穀の種が入った壺が流れ着いたというイシキ浜、外間(ふかま)ウプグィ、御殿庭(うどぅんみゃー)など島全体に点在しています。なかでも、かつて久高御殿があった御殿庭は12年毎のイザイホーが行われていた場所で、今でも村落の主要な年中祭祀の祭場となります(写真4)。なお、祭祀中は観光客が行動を制限されることがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

◆琉球王国開闢(かいびゃく)神話
琉球王国開闢神話に出てくる女神アマミキヨと男神シネリキヨは、ニライカナイ(海の彼方にある神界)から久高島へ降り立ち、国造りを始めたとされています。最初に沖縄に7つの御嶽(うたき、祭祀を行う神聖な場所)が作られ、そのうち琉球王国で最も神聖なものとされる斎場(せーふぁ)御嶽は、本島から久高島を臨む位置関係にあります(前掲写真1)。このことも久高島が沖縄におけるニライカナイ信仰の重要な場所であることを示しています。久高島で最高の聖地は島の中央部にあるフボー御嶽(写真3)で、奥には祭祀場である円形広場がありますが、現在は立ち入り禁止になっています。
久高島の祭祀の中でもよく知られるのが「イザイホー」です。久高島で生まれ育った女性が神女になる儀式のことで、琉球王国時代から400年にわたり12年毎に行われてきました。『沖縄と色川大吉』(2021年)を読むと、当時の祭祀の様子が事細かく記されており、島の人々の行事に掛ける思いも伝わってきます。しかし、この祭祀は後継者不足により1978年を最後に行われていません。それでも、久高島には今も、沖縄のほとんどで消えかけた古来の祭祀組織が残っており、年間で約30回もの祭祀があります。祭祀の行われる場所は、フボー御嶽のほかに、ニライカナイから五穀の種が入った壺が流れ着いたというイシキ浜、外間(ふかま)ウプグィ、御殿庭(うどぅんみゃー)など島全体に点在しています。なかでも、かつて久高御殿があった御殿庭は12年毎のイザイホーが行われていた場所で、今でも村落の主要な年中祭祀の祭場となります(写真4)。なお、祭祀中は観光客が行動を制限されることがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

写真3:フボー御嶽


写真4:御殿庭。左奥のバンカイヤーという建物はイラブー(エラブウミヘビ)の燻製施設
◆島のまちなみ
集落には琉球石灰岩を使った石垣や石畳、琉球赤瓦を使った屋根といった沖縄の伝統的なまちなみが見られます。石垣は、「野面(のづら)積み」といわれる自然の形のまま積み上げたものと、「相方(あいかた)積み」といわれる多角形に加工した石を互いにかみ合うように積み上げたものがあり、通りの印象に変化をもたらしています。また、沖縄の伝統的な建築様式の一つであるヒンプン(写真5)を設けている家も見られます。家の正面にある目隠し塀のことで、魔除けや風よけなどの役割もあります。
集落には山村留学を受け入れる「久高島留学センター」が2001年に開設されています。かつては久高小中学校に通う中学生がわずか2名まで減少するという統廃合の危機もありましたが、現在では全国各地の留学生を毎年10数名受け入れているそうです。


◆島のまちなみ
集落には琉球石灰岩を使った石垣や石畳、琉球赤瓦を使った屋根といった沖縄の伝統的なまちなみが見られます。石垣は、「野面(のづら)積み」といわれる自然の形のまま積み上げたものと、「相方(あいかた)積み」といわれる多角形に加工した石を互いにかみ合うように積み上げたものがあり、通りの印象に変化をもたらしています。また、沖縄の伝統的な建築様式の一つであるヒンプン(写真5)を設けている家も見られます。家の正面にある目隠し塀のことで、魔除けや風よけなどの役割もあります。
集落には山村留学を受け入れる「久高島留学センター」が2001年に開設されています。かつては久高小中学校に通う中学生がわずか2名まで減少するという統廃合の危機もありましたが、現在では全国各地の留学生を毎年10数名受け入れているそうです。


写真5:相方積みの石垣とヒンプン(左)と野面積みの石垣(右)
◆土地総有制
久高島では、国有地や電力会社の用地を除き、「字久高」名義で土地を登記・所有する「土地総有制」がとられています。琉球王朝からの「地割制」が県内で唯一残る地域で、明治32年(1899年)に実施された沖縄県土地整理事業でも、土地の私的所有には移行せず、総有制を守り続けました。その後、土地の利用実態や管理方法の変遷を踏まえ、1989年に「土地憲章」が制定されました。それまでの慣習を整序し、新たな土地利用の発生を考慮して規範を刷新したものです。もちろん、居住地や農地も利用権を有するのみです。なお、土地所有主体である「字久高」の構成員は、おおむね自治会の久高区と重なっていますが、完全には一致しません。たとえば、久高区の住民であっても、構成員資格(3年の居住要件)を満たしていなければ「字久高」の構成員にはなりません。この「土地総有制」により、久高島はリゾート開発などの乱開発から守られてきたと言えます。
◆島民との思いがけない交流
島を一通り回り終えた夕暮れ時、海の見える港近くのベンチでゆんたく(おしゃべり、団らん)している3人の年配男性から「一緒に飲もう!」と声を掛けられました。島民と話す絶好の機会を逃すまいと応じたところ、オリオンビールに古酒(くーす)、手作りの料理までご馳走になり、島での暮らしやその変化について聞くことができました。薦められた食堂でイラブー汁を堪能した後、宿泊先の久高島宿泊交流館へ戻ると、入口横のテントに出現した「居酒屋てぇげぇぐゎー」(てぇげぇはテキトー、ぐゎーは小さなもの)から、今度は4人の年配男性に誘われました。久高島の方言を教えてもらったり、三線(さんしん)を弾かせてもらったり、素手でイラブ―(※有毒)を捕る方法を教えてもらったり、ヤシガニと星空を観るナイトツアーに連れて行ってもらったりと、想像もしていなかった楽しい時間を過ごすことができました(写真6)。
今回初めて訪れた久高島は、「神の島」という名前から想像していた張り詰めた空気感とは違って、優しい光に包まれた温かい雰囲気の島でした。私たちのように島に宿泊する人は多くありませんが、久高島には年間4万人を超える観光客が訪れています。観光振興が島の生活・文化の維持を妨げないこと、さらにはプラスの効果をもたらすことを切に願っています。

>> HOME
◆土地総有制
久高島では、国有地や電力会社の用地を除き、「字久高」名義で土地を登記・所有する「土地総有制」がとられています。琉球王朝からの「地割制」が県内で唯一残る地域で、明治32年(1899年)に実施された沖縄県土地整理事業でも、土地の私的所有には移行せず、総有制を守り続けました。その後、土地の利用実態や管理方法の変遷を踏まえ、1989年に「土地憲章」が制定されました。それまでの慣習を整序し、新たな土地利用の発生を考慮して規範を刷新したものです。もちろん、居住地や農地も利用権を有するのみです。なお、土地所有主体である「字久高」の構成員は、おおむね自治会の久高区と重なっていますが、完全には一致しません。たとえば、久高区の住民であっても、構成員資格(3年の居住要件)を満たしていなければ「字久高」の構成員にはなりません。この「土地総有制」により、久高島はリゾート開発などの乱開発から守られてきたと言えます。
◆島民との思いがけない交流
島を一通り回り終えた夕暮れ時、海の見える港近くのベンチでゆんたく(おしゃべり、団らん)している3人の年配男性から「一緒に飲もう!」と声を掛けられました。島民と話す絶好の機会を逃すまいと応じたところ、オリオンビールに古酒(くーす)、手作りの料理までご馳走になり、島での暮らしやその変化について聞くことができました。薦められた食堂でイラブー汁を堪能した後、宿泊先の久高島宿泊交流館へ戻ると、入口横のテントに出現した「居酒屋てぇげぇぐゎー」(てぇげぇはテキトー、ぐゎーは小さなもの)から、今度は4人の年配男性に誘われました。久高島の方言を教えてもらったり、三線(さんしん)を弾かせてもらったり、素手でイラブ―(※有毒)を捕る方法を教えてもらったり、ヤシガニと星空を観るナイトツアーに連れて行ってもらったりと、想像もしていなかった楽しい時間を過ごすことができました(写真6)。
今回初めて訪れた久高島は、「神の島」という名前から想像していた張り詰めた空気感とは違って、優しい光に包まれた温かい雰囲気の島でした。私たちのように島に宿泊する人は多くありませんが、久高島には年間4万人を超える観光客が訪れています。観光振興が島の生活・文化の維持を妨げないこと、さらにはプラスの効果をもたらすことを切に願っています。

写真6:ピザ浜から見た朝日
(文責・写真:樋野公宏・綾美)
◆参考文献
・南城市ホームページ
・三木健編『沖縄と色川大吉』, 不二出版, 2021年
・小川竹一「久高島の土地総有制の意義」, 地域研究, 13, 195-212, 2014年
・比嘉康雄『日本人の魂の原郷 沖縄久高島』, 集英社新書, 2000年
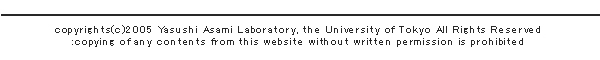
(文責・写真:樋野公宏・綾美)
◆参考文献
・南城市ホームページ
・三木健編『沖縄と色川大吉』, 不二出版, 2021年
・小川竹一「久高島の土地総有制の意義」, 地域研究, 13, 195-212, 2014年
・比嘉康雄『日本人の魂の原郷 沖縄久高島』, 集英社新書, 2000年